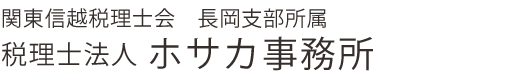税務相談Q&Aテキスト版
2022年12月号
▼テーマ
年の途中で亡くなられた方の確定申告
▼本文
通常、各年の所得税は翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告により申告・納税することとなっています。
しかし、年の途中で亡くなられた方の、1月1日から亡くなる日までの間の所得については「準確定申告」という手続きにより申告・納付することとなります。
準確定申告が必要な場合
準確定申告が必要かどうかの判断は通常の確定申告の場合と同様です。事業所得や不動産所得等があり、毎年確定申告をされていた方は、準確定申告が必要であると考えられます。
公的年金等の収入金額が四百万円以下であり、公的年金等以外の所得が20万円以下である場合等は準確定申告は不要となります。準確定申告書は原則として相続人全員の署名により、亡くなった方の納税地の税務署に提出します。
申告期限
① 準確定申告の期限は、相続の開始があった事を知った日の翌日から4カ月以内です。例えば、相続の発生が5月1日だったとします。この場合の申告の期限は、9月1日になります。
② 相続の発生が1月1日から3月15日までで、その時点でまだ前年分の確定申告をしていなかった場合には、前年分と本年分の両方の申告をしなければなりません。この場合の申告期限も前年分、本年分ともに相続の発生の日から4カ月以内となります。
所得控除
① 医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の対象となるのは、亡くなった本人が死亡の日までに支払った医療費や保険料に限られます。
死亡後に親族が支払ったものについては控除の対象となりません。
② 配偶者控除、扶養控除は配偶者や親族の年間所得により適用できるかどうかが決まります。年の途中での手続きとなるため、死亡日時点での年間所得の見積額により、適用の有無を判断します
2022年05月号
▼テーマ
相続税の申告の対象となる財産と注意すべき預貯金
▼本文
相続税の対象となる財産は、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。相続税の財産は、
民法上の財産(「本来の相続財産」)と相続税の課税の公平の見地から課税の対象となる財産(「みなし相続財産」)があります。
① 本来の相続財産
本来の相続財産(民法上の相続財産)には次のような財産が該当します。
- 現金、預貯金
- 貸付金
- 有価証券
- 不動産と不動産上の権利(土地建物、借地権等)
- 各種動産(自動車、宝石、書画骨董品)
- ゴルフ会員権
- 未収金(配当金、高額療養費)
- その他(事業用財産、家庭用財産)
② みなし相続財産
みなし相続財産には相続税法の規定において次のものがあります
- 死亡保険金
- 生命保険契約に関する権利
- 死亡退職金
- 定期金に関する権利他
③ 預貯金の相続税の申告をする際の注意点
被相続人の預貯金
亡くなられる前に一定の金額を引出している場合注意が必要です。葬儀費用や医療費の精算のために使われたものであっても相続財産となります。
ところで、平成30年の「仮払い制度」の創設により法定相続分の3分の1まで(限度額あり)他の相続人の合意なく預金を引出すことが可能になりました。
そしてこれは相続財産として取扱うことになります。
家族名義の預金
預金の名義となっている人物と実際の預貯金の所有者が異なる預金を名義預金と言います。
財産の所有者を判定するにあたり、名義人を所有者と考えてしまい、相続財産から漏れやすくなってしまいます。被相続人が取得等のための資金を拠出していた場合、被相続人の財産と認められて相続財産になります。名義預金と認定されないようにするには名義預金を作らないことです。
どうしても家族名義にしたい場合は以下のように適切な方法で贈与する必要があります。
- 贈与契約書の作成
- 贈与の実行
- 贈与後の管理支配
- 贈与税の申告
2022年01月号
▼テーマ
個人事業等における必要経費
▼本文
個人事業等の所得税確定申告の時期が近づいてきました。所得金額を計算する上で必要経費となるものを、注意事項や特例の取扱いを踏まえて確認してみましょう。
一、必要経費に算入できる金額
事業所得等の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
① 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
② その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
二、必要経費の算入時期
必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額です。したがって、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりません。
また、支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
三、必要経費に算入する場合の注意事項
① 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(水道光熱費など)となるものがあります。この家事関連費のうち必要経費になるのは、
取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であった部分の金額に限られます。
② 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。
また、受取った人は所得としては扱われません。
③ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
所得税法上の特例として、生計を一にする配偶者その他の親族が第三者に支払った経費は、個人事業主の経費として認められています。
例えば、妻が地代家賃の支払いや固定資産税等といった経費を第三者に支払っている場合、夫が営んでいる事業の必要経費になります。
2021年08月号
▼テーマ
金地金、古銭・記念硬貨、切手などを売ったときの税金
▼本文
ここ数年、金の価格は上昇していることから、お手持ちの金を売却して利益を得る方も多いと思います。また、コロナ禍の中、巣ごもりで家の中を片付けているときに、古銭や旧札、切手などが出てきた場合、これらのものを買取業者へ売却したら税金はどうのように取り扱われるのでしょうか。
1.金地金の場合
給与所得者や年金受給者などが金地金を売却した場合は譲渡所得として課税され、給与や年金など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
譲渡所得の計算方法は次のとおりです。
①所有期間5年以内の場合
売却価額―(取得価額+売却費用)―特別控除50万円=課税される所得
②所有期間5年超の場合
(売却価額―(取得価額+売却費用)―特別控除50万円)×二分の一=課税される所得
※取得価額が分からない場合は、売却価額の5%が取得価額となります。
以上のとおり、年間の譲渡益が50万円までは特別控除の範囲内なので税金はかからないことになります。
金地金以外の総合課税の譲渡益がある場合は、それを合計した額に対しての50万円です。
2.古銭・記念硬貨の場合
生活用動産に含まれるため、基本的には課税されません。ただしプレミア価格がついたものなどを高値で売却したときは価値のある財を売却したとみなされます。1個又は1組の価額が30万円を超える譲渡の場合は課税の対象となります。
従って、30万円以下の譲渡であれば課税はされません。
課税される場合の計算方法は、前述の①、②と同様になります。
3.切手の場合
古銭・記念硬貨と同じ取り扱いになります。
古銭・記念硬貨や切手の場合は、1点が30万円を超えるものに限られます。そして、50万円の特別控除の枠があるので、ほとんどが課税の対象外になるかと思います。また、その他にも貴金属や宝石、書画、骨董なども古銭・記念硬貨、切手と同様の
取り扱いになります。
2021年05月号
▼テーマ
土地・家屋の評価と税金について
▼本文
土地や家屋を所有している方には、4月中旬に固定資産税の課税通知書が届いていることと思います。固定資産税はその年の1月1日現在の所有者等に課税されます。
また相続や贈与等により土地や家屋を取得した場合には相続税や贈与税がかかる可能性があります。今回は、土地・家屋の評価や税金について説明します。
1 固定資産税の計算方法
①固定資産税
固定資産税の計算方法は次のとおりとなっています。
「固定資産税課税標準額×1.4%=固定資産税」(長岡市の税率)
②都市計画税
土地や家屋が市街化区域内にある場合には、次の計算方法により都市計画税がさらに課税されます。
「固定資産税課税標準額×0.2%=都市計画税」(長岡市の税率)
③土地の課税標準額
土地の課税標準額については、商業地等(住宅用地以外)は調整措置により「固定資産税評価額」の通常7割となっています。
④住宅用地
住宅用地については、面積が200㎡までの部分が固定資産税評価額の6分の1,200㎡を超える部分は3分の1に軽減されます。
また、都市計画税については200㎡までの部分が3分の1,200㎡を超える部分が3分の2に減額されます。
また新築住宅である場合には家屋の評価が減額される特例もあります。
2 固定資産税評価額
固定資産税評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて次のように評価されます。
①土地の評価額
公示価格(一般の土地取引価格の指標)のおおよそ7割となっています。
②家屋の評価額
「再建築価格×経年減点補正率=家屋の評価額」
ただし、経年減点補正率には下限が定められており、耐用年数を経過した家屋でも2割は残価が残ります。
また固定資産税評価額は、不動産取得税や登録免許税の課税標準となっており、評価額が税額に影響します
3 路線価は公示価格のおおよそ8割
前項で説明したとおり、固定資産税評価額は公示価格のおおよそ7割となっています。相続税や贈与税で土地を評価するときに用いる路線価は、公示価格のおおよそ8割となっています。実際の相続税評価額は、土地の形状等により補正するので異なりますが、路線価から対象となる土地のおおよその取引価格を割り出すことができます。
なお路線価は国税庁のHPで確認することができます。
2021年03月号
▼テーマ
ひとり親控除及び寡婦控除
▼本文
社会情勢の変化や生活環境の多様化に合わせ、税制も改正がなされていきます。令和2年度税制改正では「ひとり親控除」の創設及び「寡婦(夫)控除」の見直しがなされました。今回はその内容について説明したいと思います。
1 旧寡婦(夫)控除の概要
そもそも「寡婦(夫)控除」とは、配偶者と離婚や死別をした方が受けられる所得控除でした。但しその適用には、残された配偶者が男性か女性かによって適用条件や控除額に違いがありました。そして一度は婚姻関係を持った人を前提に作られた制度であったため、過去に婚姻のない未婚のひとり親の方には適用出来ませんでした。
2 ひとり親控除
そこで令和2年度改正により、次の条件を全て満たす方に対し、「寡婦(夫)控除」に替えて「ひとり親控除」として35万円を控除する事となりました。
①現に婚姻をしていない方であること。
②生計を一にする子供(所得が48万円以下)がいること。
③本人の所得が500万円以下であること。
④事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと。
「現に婚姻をしていない方」という規定に変わったことにより、過去の婚姻歴は関係なくなり、未婚のひとり親の方も対象に加わります。
そして、今まで離婚や死別で寡婦控除を受けていた子供がいる方は、男女の区別なく「ひとり親控除」の対象に変更となります。
3 寡婦控除
旧寡婦控除で控除対象だった、生計を一にする子供のいない女性には、寡婦控除の制度を残し、次のいずれかの条件を満たす場合に27万円の控除が出来る事としました。
①夫と死別した、所得が500万円以下の現在婚姻していない女性。
②夫と離婚して子供以外の扶養親族がいる、所得が500万円以下の現在婚姻していない女性。
なお、この改正で、どちらの控除も本人の所得は500万円以下(給与年収678万円以下)に統一されています。
事実婚の状態にある方については対象外となりますのでご注意ください。